土用餅と赤福の違いが気になる方へ。
「土用の丑の日の和菓子選びで迷った」「赤福と土用餅、どちらを贈ればいいの?」と悩む方や、和菓子が好きな方、季節の行事を大切にしたい方に向けて書きました。
・土用餅と赤福、それぞれの由来や特徴
・食べる時期や地域ごとの違い
・見た目や味の比較ポイント
・贈り物や手土産におすすめなのはどっち?
・ネット通販での買い方や選び方のコツ
・よくある質問・豆知識もQ&Aで網羅
これを読めば、土用餅と赤福、「どちらを選べばいいのか」「違いは何か」が一目でわかります。
和菓子選びがもっと楽しくなりますよ。
土用餅と赤福の違いは?見た目・由来・食べる時期・食べ方を解説!
「土用餅」と「赤福」、どちらも和菓子好きにはたまらない存在ですが、具体的にどう違うのでしょう?
由来や食べる時期、見た目や味わいまで、徹底的に比較していきます。
- ①土用餅とは?由来や特徴・いつ食べるものか
- ②赤福とは?歴史や定番の食べ方・食べるタイミング
- ③土用餅と赤福の違いを比較表でチェック!
- ④それぞれのおすすめの食べ方や買える場所
土用餅と赤福は名前は知っていても、「実は違いがわかっていない・・・」という人が多い和菓子。
まずは一つずつ丁寧に解説していきますね。
①土用餅とは?由来や特徴・いつ食べるものか
土用餅(どようもち)は、特に関西地方を中心に、土用の丑の日(夏の土用の期間)に食べる和菓子です。
- 小豆あんで包まれた丸いお餅(=あんころ餅)が一般的
- 「暑気払い」や「無病息災」を願う風習として親しまれる
- 由来は江戸時代。暑さに負けないよう、滋養のある小豆を食べる習慣から
食べる時期は、毎年「夏の土用(7月下旬ごろ)」がメイン。
「土用の丑の日」に合わせて和菓子屋さんに並ぶことが多いです。
通年販売の「あんころ餅」を、土用の丑の日付近だけ「土用餅」と名前を変えて販売するお店もあります。
②赤福とは?歴史や定番の食べ方・食べるタイミング
赤福(あかふく)は、三重県伊勢の銘菓。
やわらかな餅をこしあんで包み、表面に伊勢神宮の五十鈴川をイメージした波模様が入っているのが特徴です。
- 三重県伊勢市発祥で、創業は1707年と歴史ある和菓子
- もっちりしたお餅と、なめらかなこしあんの絶妙なバランス
- 年中楽しめるが、伊勢参りの定番・手土産として大人気
食べるタイミングに決まりはなく、旅行のお土産やおやつ、お茶請けなど、いつでも気軽に食べられる和菓子です。
「お伊勢さん」といえば赤福、というイメージが定着していますね。
③土用餅と赤福の違いを比較表でチェック!
| 項目 | 土用餅 | 赤福 |
|---|---|---|
| 主な地域 | 関西中心 | 三重・全国 |
| 見た目 | 丸いお餅+あんこで包む | 細長いお餅+こしあん&波模様 |
| 食べる時期 | 夏の土用・土用の丑の日 | 通年(伊勢参り・お土産) |
| 由来・意味 | 暑気払い・無病息災祈願 | 伊勢名物・旅の無事祈願 |
| 味の特徴 | 小豆あんの素朴な甘さ | なめらかなこしあん+もっちり餅 |
④土用餅と赤福はどこで売ってる?食べ方は?
土用餅は和菓子屋さんやデパ地下で、主に夏限定で販売。
特に土用の丑の日が近づくと、店頭にズラリと並びます。
土用の鰻とともに、セブンイレブンなどのコンビニに並ぶこともありますよ。
冷たいお茶と一緒に食べるのが定番!
一方赤福は、伊勢神宮周辺の本店や直営店、百貨店・駅の売店などで一年中購入できます。
お土産用の折箱や、現地で食べられる赤福氷(夏季限定のかき氷)も大人気。
家族や友人とシェアするのも楽しいですよ。
土用餅と赤福、どっちがおすすめ?選び方ガイド
「土用餅と赤福、どっちを選べばいいの?」と悩む方も多いですよね。
用途や季節、贈る相手、シーンによってぴったりの選び方をご紹介します。
- ①贈り物や手土産に向いているのは?
- ②季節や行事で選ぶならどっち?
- ③日持ちや価格の違い
どちらも美味しいですが、それぞれにおすすめのシチュエーションがあります。
①贈り物や手土産に向いているのは?
赤福はパッケージも美しく、有名な伊勢の銘菓として全国的にも喜ばれる一品。
遠方への手土産や贈り物としても安心です。
- 赤福:家族や友人、会社の方へのお土産・贈答用にも最適
- 土用餅:旬の季節限定感があるので、和菓子好きな方や目上の方への季節のご挨拶におすすめ
土用餅は関西圏での季節の贈り物や、「暑気払い」や「無病息災を願う」意味を込めたギフトとして選ばれています。
②季節や行事で選ぶならどっち?
土用餅は「夏の土用」「土用の丑の日」に合わせて食べるのが伝統的。
期間限定の特別感を楽しみたいならこちらがおすすめです。
赤福は通年楽しめますが、伊勢参りや旅行の記念、正月やお祝いごとにもぴったり。
特に伊勢に行った時は「絶対に買う!」という人も多いですね。
- 土用餅:夏の土用の時期に
- 赤福:旅行・季節を問わず、伊勢土産や年中行事に
③日持ちや価格の違い
| 項目 | 土用餅 | 赤福 |
|---|---|---|
| 日持ち | 2〜3日程度(生菓子なので早めに) | 2〜3日程度(夏場は短い) |
| 価格帯 | 1個100〜200円程度 | 8個入りで900円程度 |
| 購入場所 | 和菓子店・百貨店(主に夏) | 伊勢・百貨店・駅売店など |
どちらも日持ちはあまり長くありませんが、作りたての美味しさが魅力。
手に入る時期や場所も参考に、ぜひ味わってみてくださいね。
土用餅と赤福にまつわるよくある質問Q&A
「土用餅と赤福、なんとなく似てるけどどう違う?」
「実はこんな時に食べてもいい?」
など、よくある疑問や豆知識をQ&Aでまとめました。
気になるギモンを一気に解決しましょう!
- ①赤福を土用餅として食べてもいい?
- ②土用の丑の日と赤福の関係は?
- ③関西と三重、地域ごとの違いは?
- ④それぞれのカロリーやアレルギー情報
①赤福を土用餅として食べてもいい?
赤福も餅とあんこの和菓子なので、「土用餅っぽいから」と夏の土用に食べる人もいます。
厳密には別の和菓子ですが、赤福を夏バテ対策や無病息災の願掛けに食べるのも、和の楽しみ方の一つです。
お好みで自由に楽しんでOKです!
②土用の丑の日と赤福の関係は?
赤福自体は土用の丑の日とは関係はありません。
土用の丑の日に限定される和菓子ではありませんが、伊勢周辺では夏の土用の期間にも人気があります。
土用餅が夏の土用の定番和菓子として並ぶ一方、赤福も冷たくして食べたり、赤福氷(かき氷)として夏に楽しむ人が多いです。
③関西と三重、地域ごとの違いは?
土用餅は主に大阪・京都など関西圏での夏の風習。
ただ、最近ではスーパーやコンビニでも取り扱われるようになり、全国的に知られるようになりました。
赤福は、三重県伊勢市発祥。
今では全国で有名ですが、特に東海地方や伊勢参りに縁があります。
地域によって、土用餅を販売する店や赤福の認知度にも差があるのが面白いところです。
④それぞれのカロリーやアレルギー情報
一般的な土用餅1個のカロリーは約100~150kcal前後。
赤福1個は92kcal。
どちらも主原料は、小豆・餅・砂糖です。
小麦や乳、卵は基本的に使われませんが、アレルギーが心配な場合は必ず各店舗の表示をチェックしましょう。
土用餅・赤福はネットで買える?通販での購入方法
「近くに売っていない」「ギフトで送りたい」という方は、ネット通販がとても便利です。
最近は、土用餅も赤福もオンラインで買える機会が増えてきています。
土用餅の通販・お取り寄せ
夏の土用が近づいたら、通販で取り扱いが増えます。
ネット通販では、冷蔵品と冷凍品の両方がありますが、すぐに食べるなら冷蔵で、日持ちさせたいなら、冷凍を選びましょう。
あんころ餅を土用餅として食べることもできます。
赤福の通販・お取り寄せ
赤福は賞味期限の短い生菓子です。
夏の消費期限は製造日共2日間、冬は3日間です。
基本的には、お店で買ってすぐに食べることをオススメします。
ただし、冬期(10月初旬〜5月下旬頃)のみ、伊勢より宅配可能です。
しかし、配送の翌日に届かない地域には配送されないので、ご注意ください。
お取り寄せ可能な時期・地域については、赤福公式サイトでお確かめください。
まとめ|土用餅と赤福の違いと楽しみ方
土用餅も赤福も、それぞれに由来や食べる時期、味わいの魅力が詰まった和菓子です。
お好みはあるでしょうが、違いを知ってシーンに合わせて選べるのが和菓子好きの特権!
最後にもう一度、ポイントをおさらいしましょう。
| 項目 | 土用餅 | 赤福 |
|---|---|---|
| 食べる時期 | 夏の土用(7月中旬〜下旬) 主に土用の丑の日 |
通年(特に伊勢参りや旅の記念に) |
| 由来・意味 | 暑気払い・無病息災祈願 | 伊勢神宮参拝の定番土産・旅の無事祈願 |
| 見た目・味 | 丸いお餅をあんこで包む 素朴で優しい甘さ |
こしあん+波模様の細長い餅 なめらかなあんともちもち食感 |
| 買える場所 | 和菓子店・百貨店(夏限定) 一部オンライン通販 |
伊勢本店・直営店・百貨店・通販(冬のみ) 赤福氷(夏季限定)も人気 |
- 土用餅は夏の厄除けスイーツ、赤福は伊勢名物・オールシーズンOKの和菓子
- 伊勢の手土産なら赤福、土用の丑の日付近なら土用餅がおすすめ
- ネット通販も活用すれば、どちらも気軽に手に入る
和菓子を通して季節の行事や伝統を味わえるのも日本文化の醍醐味。
どちらも機会があれば、ぜひ食べ比べてみてくださいね。
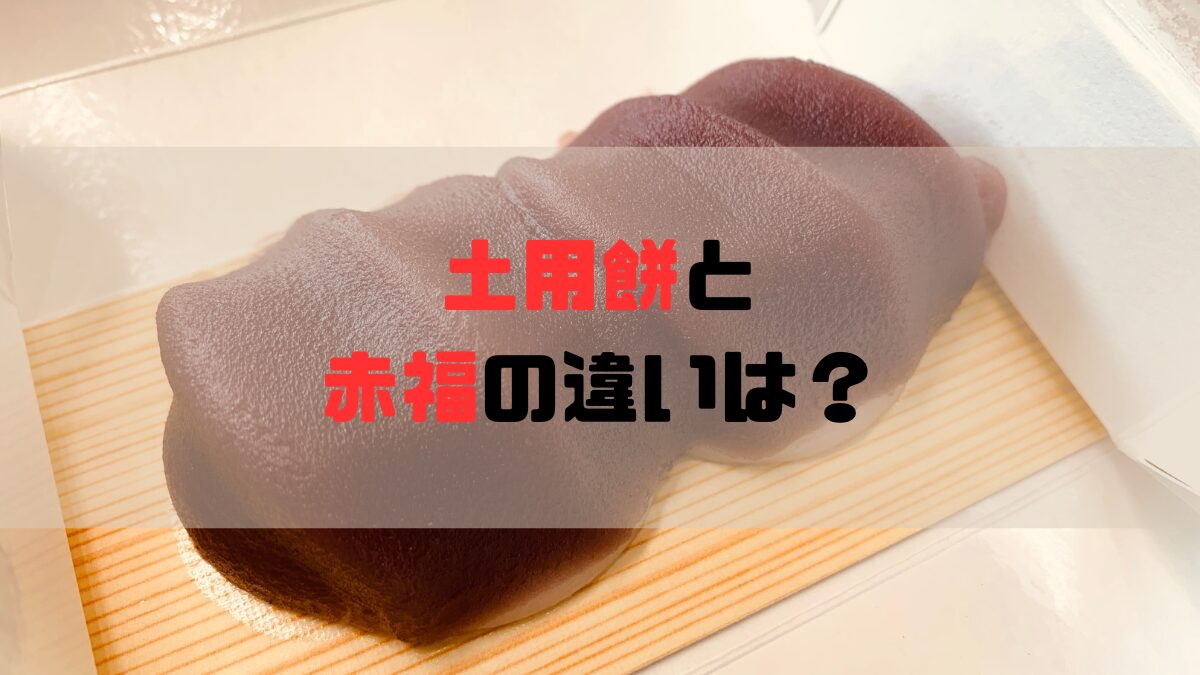

コメント